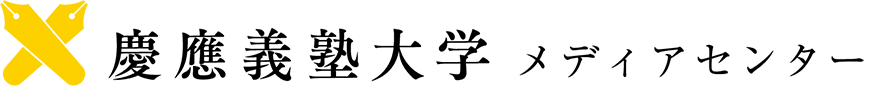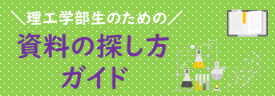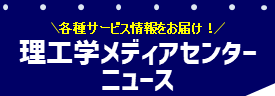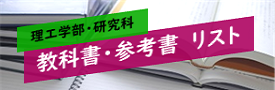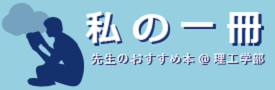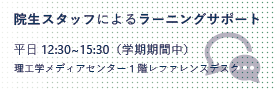図書館紹介
理工学メディアセンター概要
未来へつなぐ科学技術創発の拠点
理工学メディアセンター(松下記念図書館)は、松下電器産業(現パナソニック)株式会社の創業者である松下幸之助氏の篤志により1971年に建設されました。理工学分野の専門図書館として国内有数の規模を誇り、学外の研究者にも広く公開しています。電子ジャーナルや電子ブック、データベース、学位論文などの電子資料の提供やさまざまな非来館型のサービスの充実により、理工学分野の研究を支援しています。また、夜間や日曜日にも利用が可能な自習室、広めの個人ブース、部屋の壁全体がホワイトボードのグループ学習室など、学習スペースの整備にも力を入れています。さらに、各種セミナーや大学院生スタッフによる学習サポートなど教育・研究を支援するサービスを年間を通して提供しています。
沿革
理工学部の前身である工学部の祖、藤原工業大学は、1939年、現在の日吉キャンパスの図書館や第4校舎が建てられている場所に開設されました。その校舎におかれた、徳川武定子爵旧蔵の「戸定文庫」を中心とした図書室が、理工学メディアセンターの始まりとなった「工学部図書室」です。1944年、藤原工業大学は義塾に寄附移管され大学工学部が設置されましたが、1945年4月の空襲により、校舎もろとも図書室は灰塵に帰してしまいました。学生はその後しばらくの間、藤山愛一郎氏より寄付された芝白金の「藤山工業図書館」を使っていたと言われています。
1949年3月、小金井への校舎移転が決まると図書室の設置が計画されました。1952年4月30日には鉄筋コンクリート2階建ての書庫と木造モルタル造りの閲覧室からなる「工学部図書室」が、機械工学科教授室と同居する形で開設されました。その後、慶應義塾図書館規程の中央図書館制度の下に1958年4月から「図書館小金井分室」と称していましたが、1965年10月25日、分室は「慶應義塾工学図書館」に昇格し、初代館長に高橋吉之助が就任しました。この頃から専門の図書館員が配置され、資料室的な機能しか持たなかった保存中心の図書室から、開架式で相互貸借を行うサービス志向型の図書館へと変わっていきました。
工学部図書館にとって大きな転機となったのは、小金井キャンパスから矢上台(横浜市・現在の矢上キャンパス)へ工学部が移転したことです。1971年9月に松下電器産業(現 パナソニック)株式会社の創業者である松下幸之助氏からの寄附により、現在の本館(15棟)にあたる煉瓦色の建物が建設され、同年10月4日から図書館業務を開始しました。その建物は鉄筋3階建て、延床面積2,300㎡で、「松下記念図書館」と命名されました。閲覧席は270席、図書収蔵力は建設当初88,000冊であり、学部の図書館として当時国内屈指の規模でした。特にロシア語の雑誌は国立国会図書館と双璧を成していました。
1989年に厚生棟(16A棟)地階に書庫(403㎡)を増設し、本館との連絡通路を設け別館としました。2000年には新築された「創想館」(14棟)の1階(527㎡)と地下1階(290㎡)にエリアを拡張し、現在に至ります。大学の教育・研究の変化に伴い、電子情報環境を整備する一方、館内には多様な学習スタイルに合わせた空間を設けサービスを展開しています。
学内の図書館・研究室の蔵書を組織的に統合管理するため、1970年、慶應義塾に「研究・教育情報センター」が発足し、1972年に松下記念図書館の組織名は「理工学情報センター」となりました。そして1993年、塾内の組織改編を経て、さらに「理工学メディアセンター」と改めました。
理工学メディアセンターの歴史については、理工学メディアセンターニュース(No.158 - No.170)でもご紹介しています。
理工学部の歴史を知るには
- デジタル画像で理工学部の歴史をご覧いただける「写真で辿る理工学部の歴史」を公開しています。
- 『慶應義塾大学理工学部75年史』(請求記号 377@K6@1-2014)など理工学部の年史は、本館1階慶應関係図書コーナーに配架されています。
理工学メディアセンターの歴史を知るには
松下記念図書館開館50年記念企画Webページの各コンテンツをご参照ください。
また、記念小冊子「写真でたどる理工学メディアセンターのあゆみ(PDF)」を公開しています。当時の写真とともに年表形式で理工学メディアセンターの歴史をたどることが出来ます。(2022年3月刊行)